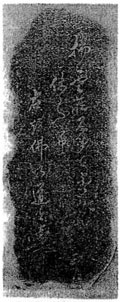
松島榮治シリーズ『嬬恋村の自然と文化』(四十)
抜け道の碑
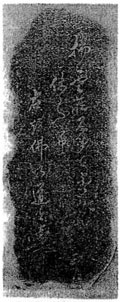 |
|
▲抜け道の碑「碑文」拓影
|
近世の関所は、江戸警備のために設けられたものであった。このため、「入鉄砲に出女」と言われ、江戸への武器の持込みと、参勤交代で江戸在住を義務づけられた諸大名の妻や娘の江戸脱出を防ぐ意図があり、共に謀叛の前兆として重点的に取り締まった。特に女性の通行には厳しかった。
大笹関所の場合も別ではなかった。元禄14年(1701)の「御関所男女出入改日記」には、女性の通過だけが、特に詳細に記録されているがそれは関所設置の意図を強く反映したものであろう。
関所の通過には、代官や名主などの発行する身分や旅の目的を示した“関所手形”が必要であった。また通行は昼間に限られていた。このため、手形を持たない者や夜間の旅人は、間道を利用することもあったが、それは「関所破り」として重罪に処せされた。
しかし、その掟も時代が下がるにつれて弛み、決まり通りには運用されなかった。「抜け道」の出現である。大笹関所の場合は“女道”とも呼んだ。この道は、大笹宿の手前から南方に浅間山麓を迂回して、長井河原に出て本通りに合するものであった。ところで、この道は広大な浅間山録の一部を過るため、地理に疎い旅人には、不安なしかも危険な道であった。
こうした女道の路傍に、嘉永5年(1852)一基の石碑が建てられた。碑は高さ80センチ程の自然石安山岩で、その正面には
「嘉永五 壬子歳 五月吉日
馬頭観世音 佐藤五兵衛 建之」
とあり、左正面には
| 揚雲雀見聞てこゝに休ふて |
| 右を仏の道と志るべし 正道 |
と刻まれている。
「仏の道」とは、善光寺道のことであり、女道とされる抜け道の「道しるべ」としたものである。建碑者佐藤正道は、大笹宿の俳人であったが、正道の豊かな詩情と時代の背景は、この風流な碑を生んだのであった。
事情あって、この道を辿る幾多の旅人が、この碑に安堵の胸をなで下ろしたに違いない。
※この記事は広報つまごいNo.563〔平成11年(1999年)10月号〕に記載されたものです。